料理を始めると、初期の段階でよく「さしすせそ」の順番で味を入れる。と聞きますよね?昔から言われていますが、意外と理由も分からずなんとなく使ってしまう方もいると思います。
主に煮物の味付けの際に、使われる定義ですが、原理を理解しているとさらに上達できます。
また、ここにはない酒とみりんはいつ入れるのか?についてもご紹介していきます。
さしすせそ
すでにお分かりの方も多いと思いますが、調味料から説明していきます。
「さ」→砂糖
「し」→塩
「す」→酢
「せ」→しょうゆ
「そ」→みそ
少し強引な部分もありますが、以上です。
煮物の味付けはこの順番で入れると、味付けが決まる。と言われています。
理由
これは、粒子の大きさが要因です。
「さしすせそ」の順番で粒子が大きくなると言われています。
なので、砂糖よりも先に塩を入れてしまうと、粒子の大きい塩が食材に浸透してしまい、蓋の役割をし、砂糖が浸透しにくくなってしまいます。
「すせそ」の3種類はすべて発酵食品です。
発酵食品は熱を入れてしまうと、発酵により生まれた栄養が損なわれてしまうと言う意味もあると考えられます。
ただ、それぞれ煮込むことによって味がまろやかになったりするので、栄養や風味を大切にしたい場合は最後にもう一度入れる方が良いでしょう。
注意点
最初に入れる砂糖には、食材を固める効果があります。
そのため、食材が柔らかくなってから入れないと、そこから食材があまり柔らかくなりません。
根菜類はしっかりと下茹でし、固い肉などは柔らかくなるまで煮込む必要があります。
必ず、食べられる固さになってから味を入れる事を癖付けましょう。
酒とみりんのタイミング
「さしすせそ」は理解したけど酒とみりんは?となりますよね。
以前に効果をまとめたものがあるのでご参照ください。
酒は先に入れることで、食材が柔らかくなったり、味が染み込みやすくなります。
なので、先に入れます。
みりんは、アルコールの力で食材の浸透性を上げますが、糖が多いため、どちらかというと固める力の方があるため、後半に入れます。
最後に入れることで、照りや風味が増します。
「酒」は最初、「みりん」は最後と覚えておいた方が良さそうです。
まとめ
「さしすせそ」はほぼ煮物に対する味付け方法ですが、この考え方を理解していれば、他の料理でも応用が利きます。
煮物上達のためには、「さしすせそ」だけでなく、酒、みりんの効果も理解し、下茹での知識も身につけなくてはなりません。
ひとつひとつ覚えていけば決して難しい事ではないのですが、理解していないと上手くいきません。
実践も大切ですが、頭で理解することも料理上達には欠かせません。


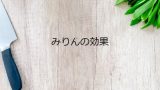


コメント
[…] […]
[…] […]